平成28年度 全国学力・学習状況調査を読む
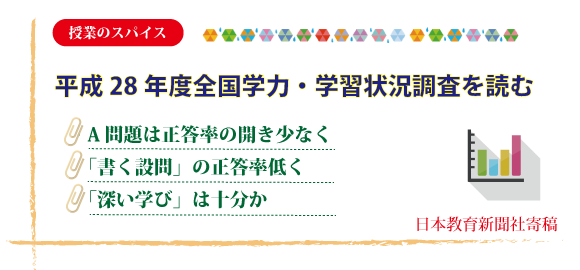
OECD国際学力到達度調査、いわゆるPISA調査の成績低迷を受け、平成19年度に復活した全国学力・学習状況調査が10年目を迎えた。今年8月公表予定のはずが集計漏れなどのアクシデントにより延期となり、文科省は9月29日に調査結果を公表した。国公私立の小学校約2万校の6年生約103万人、中学校約1万校の約104万人が今年4月に調査に挑んだもの。その結果、成績上位県は例年通りでほぼ固定化し、上位県と下位県との差が縮小した。全体の学力の底上げにつながっていると分析されている。その一方で、学力調査のうち、活用力を測る「B問題」は例年同様、平均正答率に課題を残した。なお、4月に発生した熊本地震の影響で、熊本、宮崎、大分各県の一部の小・中学校は実施を見送り、今回の数値には反映されていない。
■A問題は正答率の開き少なく
公立学校の都道府県別の平均正答率の上位を概観する。
基礎力の定着をみるA問題。小学校の国語Aは石川、広島、秋田の順で上位を占めた。同様に、算数Aは石川と福井がトップを分け合い、秋田が続いた。
中学校の国語Aは秋田、石川、富山の順。数学Aは福井、秋田に兵庫が続いた。
活用力を測るB問題。小学校の国語Bでは秋田、石川、福井、算数Bでは石川、福井、秋田の順だった。中学校の国語Bは秋田、石川、富山、数学Bは福井、富山、石川と、活用力では常連県が成績上位を占めた。
トップスリーに入った小・国語Aの広島、中・数学Aの兵庫は前回調査でも上位とは僅差で続いていた。
上位校と下位校との差を見ると、B問題では10ポイントを超える差のある教科はあったが、A問題に関してはポイント差が一ケタ台に収まるなど、全体としての開きは少なくなってきた。
■「書く設問」の正答率低く
今回も、活用力を測るB問題には、課題を残した。特に、平均正答率では「書く設問」に低率が目立った。
幾つかを具体的に挙げてみる。
小学校の国語B問題では、「山下さん」が地域のスーパーマーケットの店長にインタビューする際に事前に用意したメモと、実際にしたインタビューの一部から、インタビュー中のやりとりで空欄となった「山下さん」の質問内容を類推して「三十字以上、五十字以内」で書くことを求めた設問。この平均正答率は50・6%で最も低い設問になった。調査報告では「話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って質問することに課題がある」と指摘した。
また、小学校の国語B問題で最も無答率が高かったのも「書く設問」だった。「パン職人」の仕事について書かれたものと、「パン職人」のインタビュー記事、これらを読んだ「谷口さん」の「特に心に残ったこと」を基に、文章化されている「苦労」に対比する形で空欄として提示された「喜び」の内容を記述するよう課した設問である。無答率は11・5%。これに関しては「目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読むことに課題がある」と分析した。
小学校の算数B問題では「除法の式を、並べてできた形と関連付け、角の大きさを基に、式の意味を説明することに課題がある」設問。平均正答率は7%と最も低い。
三角定規で作った二等辺三角形を三つ並べて正三角形になったとき、なぜ三つでぴったりできるのかと先生に問われ、「360÷120」で「割り切れるからです」と答える女児。先生が「360÷120」は「どのような計算をしている式」かの説明をさらに求めた設問である。
中学校も傾向は同じ。「書く設問」が苦手だ。
国語B問題では、「エレベーターで宇宙へ」という「雑誌の記事」を読み、疑問に感じたことを学校図書館でどう調べるかを中心にした設問(平均正答率49・8%)。
疑問に思ったことを「なぜ」や「どのような(に)」、「どのくらい」の言葉のいずれかを使って書き表す。さらに、調べるために必要な「本の探し方」を二つ書くことを求めた。
「資料を基にして自ら課題を決めてはいるが、課題の解決に向け、具体的な情報収集の方法を考えることに課題がある」と分析、指摘した。
いずれも「問い」自体を正しく読み、理解できる読解力とともに、自分事として思考できる力が問われている。
日常の教育活動の中でも、設問のような場面設定は生まれているはずであり、付ける力を意識し、そうした機会を捉え、問い掛ける積み重ねも必要になろう。
■「深い学び」は十分か
今回の学習状況調査では、現在検討が進む次期学習指導要領の中核をなす「主体的・対話的で深い学び」の視点による学習指導の有無について、新規項目を追加し、その状況を聞いている。
例えば、これまで受けた授業で先生から示された課題、学級やグループの中で、自分たちで立てた課題に対して、「自ら考え、自分から取り組んでいたと思いますか」との質問項目。児童・生徒共に、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計が7割を超える。
一方、学校側の回答は、同じ問いに対して「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計が、小学校で約9割、中学校で8割強と、子どもたちの認識を大きく上回り、両者のずれが垣間見える。
平均正答率との兼ね合いで分析すると、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と肯定的に回答した者ほど、平均正答率が高い傾向にあった、と分析した。
同様に、新規に自分の発表に際して自分の考えがうまく伝わるように、資料や文章、話の組み立てなどを工夫して発表していたと思いますかという問いも加えた。
肯定的な回答は、児童・生徒側は6割台、学校側も6割台に及んだ。ただ、こちらの方は、「当てはまる」とより肯定的な回答が、児童で24・1%、生徒で17・1%あり、小学校5・6%、中学校6・2%と学校側の思いをむしろ大きく上回っている。
また、前年度との授業の比較が可能な設問がある。児童・生徒が自ら学級、グループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現する学習活動を取り入れたかを聞いたものだ。肯定的に回答した学校が27年度よりも28年度には小学校で7・1ポイント、中学校で9・2ポイント、それぞれ増加した。だが、こちらも「そのような活動ができていない」と考えている児童・生徒が一定程度存在し、学校側の意識とのズレが生じていた。
家庭の経済力格差と学力との関係が課題となる中で、今回の調査では、新たに就学援助率、学習規律、学力の三重クロス分析を試みている。
その結果、▽就学援助率にかかわらず、学習指導の改善に向けた取り組みに沿った学習を児童・生徒ができていると回答した学校ほど平均正答率が高い▽就学援助率にかかわらず、熱意をもって勉強している、私語が少なく落ち着いているなどの学習規律に関わる項目に肯定的な学校ほど、平均正答率が高い傾向にある―など、学習指導や学習規律が備われば、経済的な格差を乗り越え、学力を担保できることが明らかになった。
■悉皆、継続への批判はあるが
今回の対象教科は「国語」、「算数・数学」で、いわゆる悉皆調査として実施した。全国調査の開始後、10年の間には対象教科も改善し、平成24年度、27年度と3年に一度は「理科」を加え実施するようになった。また、31年度には中学校「英語」を対象教科とし、4技能を測る調査を実施することが検討されている。復活初年度となった19年度の国語、算数・数学に悉皆調査の枠組みは、21年度まで続き、22年度、24年度に抽出調査と実施希望方式を組み合わせ、25年度はきめ細かい調査、26年度からは再び、悉皆調査として実施してきた。
A問題の平均正答率が向上しているものの、B問題の平均正答率は十分に向上せず、課題が持ち越されているなど、毎年度実施していても調査結果の傾向に変化がないことなどと相まって、実施に掛かる費用に対する効果なども鑑み、一部には悉皆や毎年度実施など調査の在り方に疑問を呈する向きもある。10年目という節目を迎えたことを踏まえての見直し論である。賛否はあるにしても、調査が継続する限り、各学校には結果を分析、自校の学力の実態を把握し、PDCAサイクルをいかに有効に回していくか、問われ続ける課題である。秋田県のように少人数学習推進事業、県独自の学力調査、各学校が取り組む共同研究体制による授業研究など、成績上位県にあっても不断の努力が続けられている。
事前に文科省が注意を喚起したように、調査対策などを講じた〝よそ行きの学力〟でなく、〝普段着の学力〟を診断し、地道に指導を改善することが結局は学力向上の早道かもしれない。


